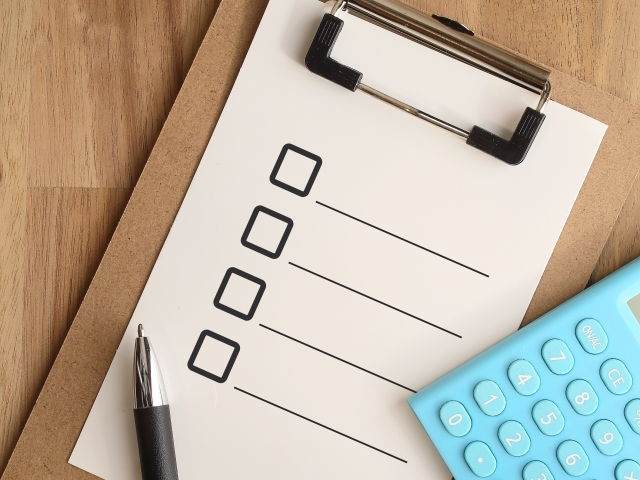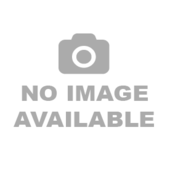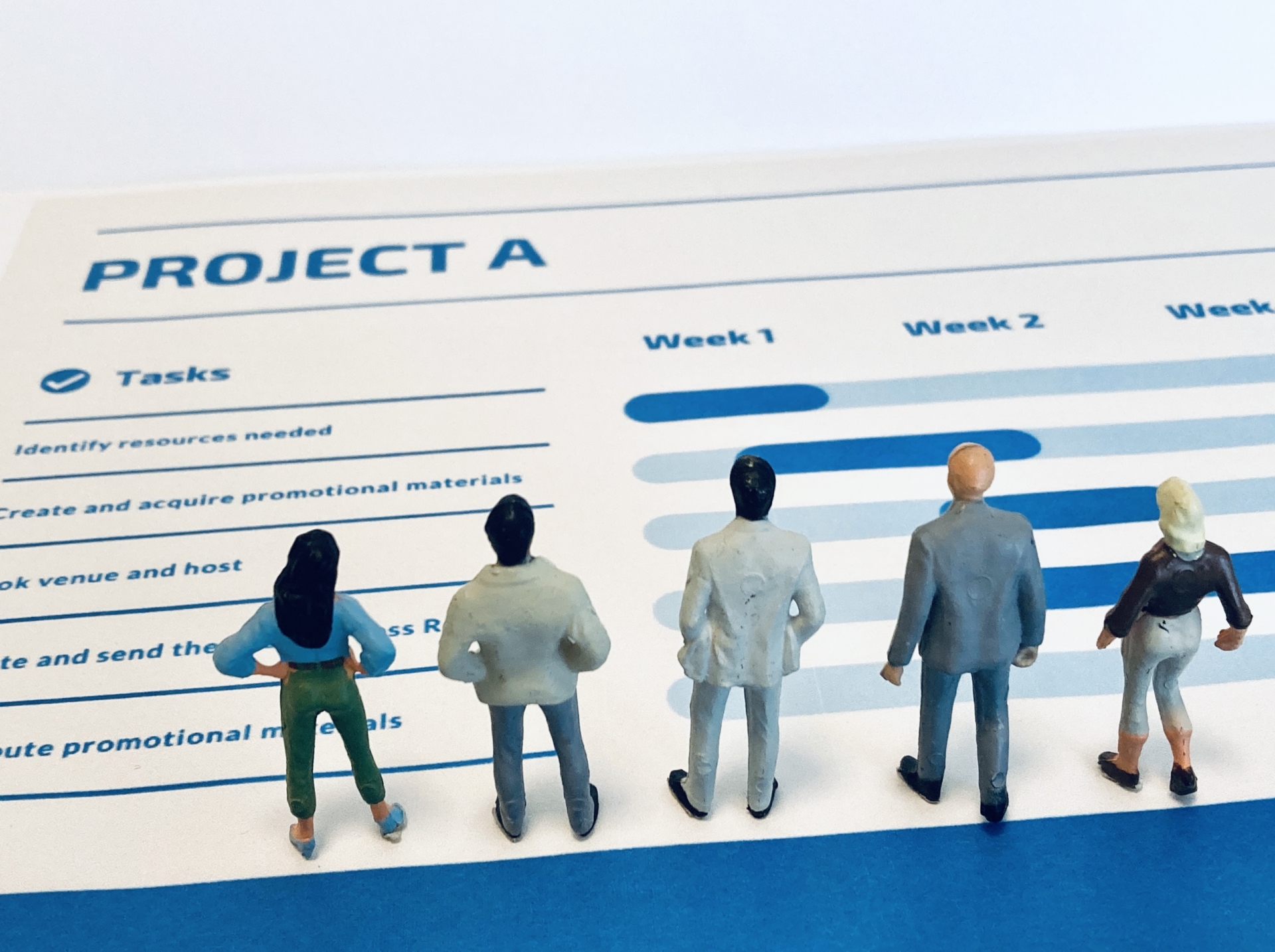гВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇгБЂгБКгБСгВЛж§ЬеПОгБ®гБѓпЉЯгГИгГ©гГЦгГЂгВТиµЈгБУгБХгБ™гБДгБЯгВБгБЃи¶БзВєгВТиІ£и™ђ
дЄАиИђгБЂгАБгВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇдЉЪз§ЊгБЂеІФи®ЧгБЧгБЯе•СзіДпЉИиЂЛи≤†е•СзіДпЉЙгБЃеЃМдЇЖгБ®гБѓгАБзЩЇж≥®еЕГгБЃж§ЬеПОгВТдї•гБ£гБ¶и°МгВПгВМгБЊгБЩгАВ
ж§ЬеПОгВТи°МгБЖгБ®гАБгБЭгБЃеЊМйБЛзФ®гГХгВІгГЉгВЇгБЂеЕ•гБ£гБ¶зЩЇи¶ЛгБХгВМгБЯдЄНеЕЈеРИпЉИгГРгВ∞пЉЙгБЂгБ§гБДгБ¶гБѓйЦЛзЩЇдЉЪз§ЊгБЃи≤ђдїїгБІдЄАеЃЪжЬЯйЦУзД°еДЯдњЃзРЖгБХгВМгВЛгБУгБ®гБЂгБ™гВЛгБУгБ®гБМдЄАиИђзЪДгБІгБЩгБМгАБгБЭгВМдї•е§ЦгБЃи¶БжЬЫгВДи™Ни≠ШйБХгБДгБЂгБ§гБДгБ¶гБѓеЯЇжЬђзЪДгБЂеИ•е•СзіДгБЂгБ¶жЬЙеДЯеѓЊењЬгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
гВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇгБЃж§ЬеПОгБ®гБДгБ£гБ¶гВВгАБе∞ВйЦАгБЃITгГБгГЉгГ†гВТжМБгБЯгБ™гБДдЉЪз§ЊгБІгБѓгВДгВКжЦєгБМеИЖгБЛгВЙгБ™гБДгБУгБ®гБМе§ЪгБПгАБйБ©ељУгБ™ж§ЬеПОгВТи°МгБДеЊМгБІгГИгГ©гГЦгГЂгБЂгБ™гВЛгБУгБ®гВВе§ЪгБДгБІгБЩгАВ
гБЊгБЯгАБгВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇгБЂгБКгБСгВЛж§ЬеПОгБЃгБУгБ®гВТеПЧеЕ•гГЖгВєгГИпЉИгГ¶гГЉгВґгГЖгВєгГИпЉЙгБ®гВВеСЉгБ≥гБЊгБЩгАВ
- гВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇгБЂгБКгБСгВЛж§ЬеПОгБ®гБѓпЉЯ
- ж§ЬеПОгБЃйА≤гВБжЦєпЉИжВ™гБДдЊЛпЉЙ
- ж§ЬеПОгБЃйА≤гВБжЦєпЉИиЙѓгБДдЊЛпЉЙ
- гБХгВЙгБЂж§ЬеПОгБЃи≥™гВТйЂШгВБгВЛгБ™гВЙ
- гБЊгБ®гВБ
гВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇгБЂгБКгБСгВЛж§ЬеПОгБ®гБѓпЉЯ
дЄАиИђгБЂгАБгВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇдЉЪз§ЊгБЂеІФи®ЧгБЧгБЯе•СзіДпЉИиЂЛи≤†е•СзіДпЉЙгБЃеЃМдЇЖгБ®гБѓгАБзЩЇж≥®еЕГгБЃж§ЬеПОгВТдї•гБ£гБ¶и°МгВПгВМгБЊгБЩгАВ
ж§ЬеПОгВТи°МгБЖгБ®гАБгБЭгБЃеЊМйБЛзФ®гГХгВІгГЉгВЇгБЂеЕ•гБ£гБ¶зЩЇи¶ЛгБХгВМгБЯдЄНеЕЈеРИпЉИгГРгВ∞пЉЙгБЂгБ§гБДгБ¶гБѓйЦЛзЩЇдЉЪз§ЊгБЃи≤ђдїїгБІдЄАеЃЪжЬЯйЦУзД°еДЯдњЃзРЖгБХгВМгВЛгБУгБ®гБЂгБ™гВЛгБУгБ®гБМдЄАиИђзЪДгБІгБЩгБМгАБгБЭгВМдї•е§ЦгБЃи¶БжЬЫгВДи™Ни≠ШйБХгБДгБЂгБ§гБДгБ¶гБѓеЯЇжЬђзЪДгБЂеИ•е•СзіДгБЂгБ¶жЬЙеДЯеѓЊењЬгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
гВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇгБЃж§ЬеПОгБ®гБДгБ£гБ¶гВВгАБе∞ВйЦАгБЃITгГБгГЉгГ†гВТжМБгБЯгБ™гБДдЉЪз§ЊгБІгБѓгВДгВКжЦєгБМеИЖгБЛгВЙгБ™гБДгБУгБ®гБМе§ЪгБПгАБйБ©ељУгБ™ж§ЬеПОгВТи°МгБДеЊМгБІгГИгГ©гГЦгГЂгБЂгБ™гВЛгБУгБ®гВВе§ЪгБДгБІгБЩгАВ гБЊгБЯгАБгВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇгБЂгБКгБСгВЛж§ЬеПОгБЃгБУгБ®гВТеПЧеЕ•гГЖгВєгГИпЉИгГ¶гГЉгВґгГЖгВєгГИпЉЙгБ®гВВеСЉгБ≥гБЊгБЩгАВ
ж§ЬеПОгБЃйА≤гВБжЦєпЉИжВ™гБДдЊЛпЉЙ
гБЊгБЪжВ™гБДдЊЛгВТжМЩгБТгБЊгБЩгАВ
гБУгВМгБѓйЦЛзЩЇдЉЪз§ЊгБЛгВЙйЦЛзЩЇеЃМдЇЖгБЃе†±еСКгБМгБВгБ£гБЯеЊМгБЂгАБйБ©ељУгБЂжАЭгБДгБ§гБДгБЯгБЊгБЊгБЂгВЈгВєгГЖгГ†гВТдљњгБДгАБдЇФжЬИйЫ®еЉПгБЂгГРгВ∞гВДи¶БжЬЫгВТжМЩгБТгАБгГРгВ∞гБМдњЃж≠£гБХгВМгБЯгВЙж§ЬеПОеЃМдЇЖгБ®гБДгБЖгВВгБЃгБІгБЩгАВ
дљХгБМжВ™гБДгБЃгБЛгБ®гБДгБЖгБ®гАБдЄїгБЂдї•дЄЛгБЃзВєгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
пЉ°пЉОж©ЯиГљгБЃзґ≤зЊЕжАІгБМдљОгБДпЉИгГЖгВєгГИгБЃжКЬгБСжЉПгВМгБМгБВгВЛпЉЙ
пЉҐпЉОгГЗгГЉгВњгБЃи≥™гБМжВ™гБДпЉИжЬђзХ™йБЛзФ®йЦЛеІЛеЊМгБЂеЃЯгГЗгГЉгВњгВТеЕ•гВМгБ¶гБѓгБШгВБгБ¶гГРгВ∞гБМи¶ЛгБ§гБЛгВЛгБ®гБДгБЖгВ±гГЉгВєгВВе∞СгБ™гБПгБВгВКгБЊгБЫгВУпЉЙ
пЉ°гБѓйЦЛзЩЇдЉЪз§ЊгБМзµРеРИгГЖгВєгГИгБ®гБДгБЖеЈ•з®ЛгБІзґ≤зЊЕзЪДгБ™гГЖгВєгГИгВТеЃЯжЦљгБЩгВЛгБѓгБЪгБІгБЩгАВ
пЉҐгБѓйЦЛзЩЇдЉЪз§ЊгБМгВЈгВєгГЖгГ†гГЖгВєгГИпЉИзЈПеРИгГЖгВєгГИпЉЙгБІжЬђзХ™зЫЄељУгБЃгГЗгГЉгВњгВТдљњгБ£гБ¶гГЖгВєгГИгВТеЃЯжЦљгБЩгВЛгБѓгБЪгБІгБЩгАВ
ж§ЬеПОгБЃйА≤гВБжЦєпЉИиЙѓгБДдЊЛпЉЙ
еЯЇжЬђзЪДгБЂгБѓжВ™гБДдЊЛгБЃйАЖгБЃдЇЛгВТгБЧгБЊгБЩгАВ
пљБпЉОзґ≤зЊЕжАІгБЃйЂШгБДгГЖгВєгГИгВТеЃЯжЦљгБЩгВЛгАВ
пљВпЉОжЬђйБЛзФ®гВТжГ≥еЃЪгБЧгБЯгГЗгГЉгВњгВТдЇИгВБзФ®жДПгБЩгВЛгАВ
пљБгБѓгАБи®≠и®ИгГХгВІгГЉгВЇдї•еЙНгБЂзФ®жДПгБХгВМгВЛгБѓгБЪгБЃж•≠еЛЩгГХгГ≠гГЉеЫ≥гБЛгВЙгАБдЄїи¶БгБ™ж•≠еЛЩгВТйБЄеЃЪгБЧгБ¶гГЖгВєгГИи®ИзФїгВТи°МгБДгБЊгБЩгАВ
гВЈгВєгГЖгГ†дЉЪз§ЊгБЃи°МгБЖгВИгБЖгБ™зХ∞еЄЄз≥їгГЖгВєгГИгБѓгВДгВЙгБ™гБДгБІгВВиЙѓгБДгБЃгБІгАБж≠£еЄЄз≥їгГЖгВєгГИгБѓдЄАйАЪгВКгБЃж©ЯиГљгВТгГЖгВєгГИгБІгБНгВЛгВИгБЖи®ИзФїгБЧгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
пљВгБѓгАБпљБгБІи®≠и®ИгБЧгБЯеРДгГЖгВєгГИи®ИзФїгБЂгБКгБДгБ¶гАБењЕи¶БгБ™гГЗгГЉгВњгВТжЬђзХ™гВТжГ≥еЃЪгБЧгБ¶зФ®жДПгБЧгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
жђ°гБЂгАБзіНеУБгГЙгВ≠гГ•гГ°гГ≥гГИгБЃж§ЬеПОгВТи°МгБДгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ зіНеУБгГЙгВ≠гГ•гГ°гГ≥гГИгБѓе•СзіДжЩВгБЂгБ©гВУгБ™гГЙгВ≠гГ•гГ°гГ≥гГИгВТзіНеУБгБЧгБ¶гВВгВЙгБЖгБЛи®ШиЉЙгБХгВМгВЛгБѓгБЪгБІгБЩгАВ
дљХгВВи®ШиЉЙгБМгБ™гБПгБ¶гВВгБЊгБ®гВВгБ™йЦЛзЩЇдЉЪз§ЊгБІгБВгВМгБ∞гАБгГЗгГЉгВњгГЩгГЉгВєйЦҐйА£гБЃи®≠и®ИжЫЄгВДзФїйЭҐдїХжІШжЫЄпЉИе§ЦйГ®дїХжІШжЫЄпЉЙгАБгГЖгВєгГИйЦҐдњВгБЃгГЙгВ≠гГ•гГ°гГ≥гГИгБѓгБВгВЛгБѓгБЪгБІгБЩгБЃгБІгАБгГ™гВѓгВ®гВєгГИгБЧгБ¶гБњгВЛгБ®иЙѓгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ
гБЯгБ†гБЧгАБгБУгВМгВТи¶ЛгБ¶дљХгБЛзРЖиІ£гВТгБЩгВЛгБЂгБѓгАБгВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇгБЃзЯ•и¶ЛгБМжЈ±гБДдЇЇеУ°гВТдЊЭй†ЉеБігБІзҐЇдњЭгБЧгБ¶гБДгБСгБ™гВМгБ∞гБ™гВКгБЊгБЫгВУгАВ
гБЊгБЯгАБWEBгВЈгВєгГЖгГ†гБІгБВгВМгБ∞гВїгВ≠гГ•гГ™гГЖгВ£гБЂгБ§гБДгБ¶гВВгБ©гБЃгВИгБЖгБ™гГЖгВєгГИгВТеЃЯжЦљгБЧгБЯгБЃгБЛгАБгГђгГЭгГЉгГИгВТгВВгВЙгБДгБЯгБДгБ®гБУгВНгБІгБЩгАВ
гБХгВЙгБЂж§ЬеПОгБЃи≥™гВТйЂШгВБгВЛгБ™гВЙ
гБУгВМгБѓдЊЭй†ЉиАЕеБігБЂгВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇгБЃе∞ВйЦАеЃґгБМгБДгВЛеЙНжПРгБІгБЩгБМгАБгВИгВКи≥™гВТйЂШгВБгВЛгБЯгВБгБЂдї•дЄЛгБЃгБУгБ®гВТеЃЯжЦљгБЩгВЛгБ®гВИгВКиЙѓгБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
гГїгВїгВ≠гГ•гГ™гГЖгВ£гГЖгВєгГИпЉИиДЖеЉ±жАІи®ЇжЦ≠пЉЙгБЃеЃЯжЦљ
гГїзХ∞еЄЄз≥їгГЖгВєгГИгБЃеЃЯжЦљ
гГїгВ§гГ≥гГХгГ©йЪЬеЃ≥жЩВгБЃеѓЊењЬгВЈгГЯгГ•гГђгГЉгВЈгГІгГ≥
гГїйА£жРЇгБЩгВЛе§ЦйГ®гВЈгВєгГЖгГ†гБЃйЪЬеЃ≥жЩВгБЃеѓЊењЬ
гБУгБ°гВЙгБЂгБ§гБДгБ¶гБѓињљгБ£гБ¶и©≥зі∞гВТи®ШиЉЙгБЧгБЯгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ
гБЊгБ®гВБ
гБУгБУгБІгБѓгВЈгВєгГЖгГ†йЦЛзЩЇгБЂгБКгБСгВЛж§ЬеПОпЉИеПЧеЕ•гГЖгВєгГИпЉЙгБЂгБ§гБДгБ¶гБЃиІ£и™ђгВДгГЭгВ§гГ≥гГИгВТи®ШиЉЙгБЧгБЊгБЧгБЯгАВ
гБУгБ°гВЙгВТеЃЯиЈµгБЧгБ¶гВВгВЙгБДгАБгГИгГ©гГЦгГЂгБЃдљОжЄЫгБЂељєзЂЛгБ¶гБЯгВЙеєЄгБДгБІгБЩгАВ