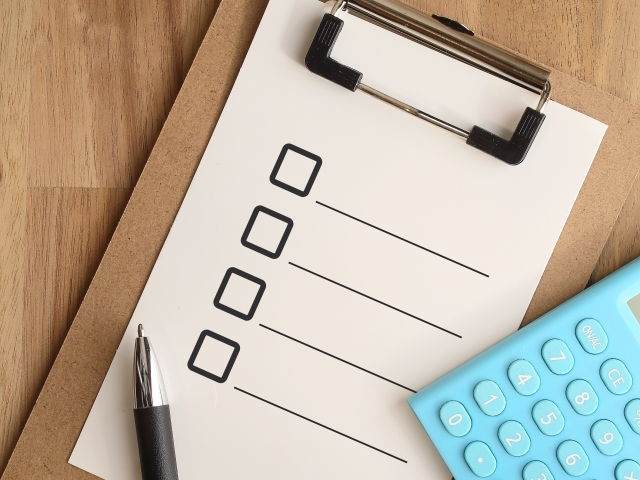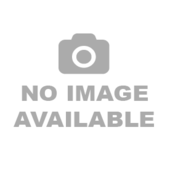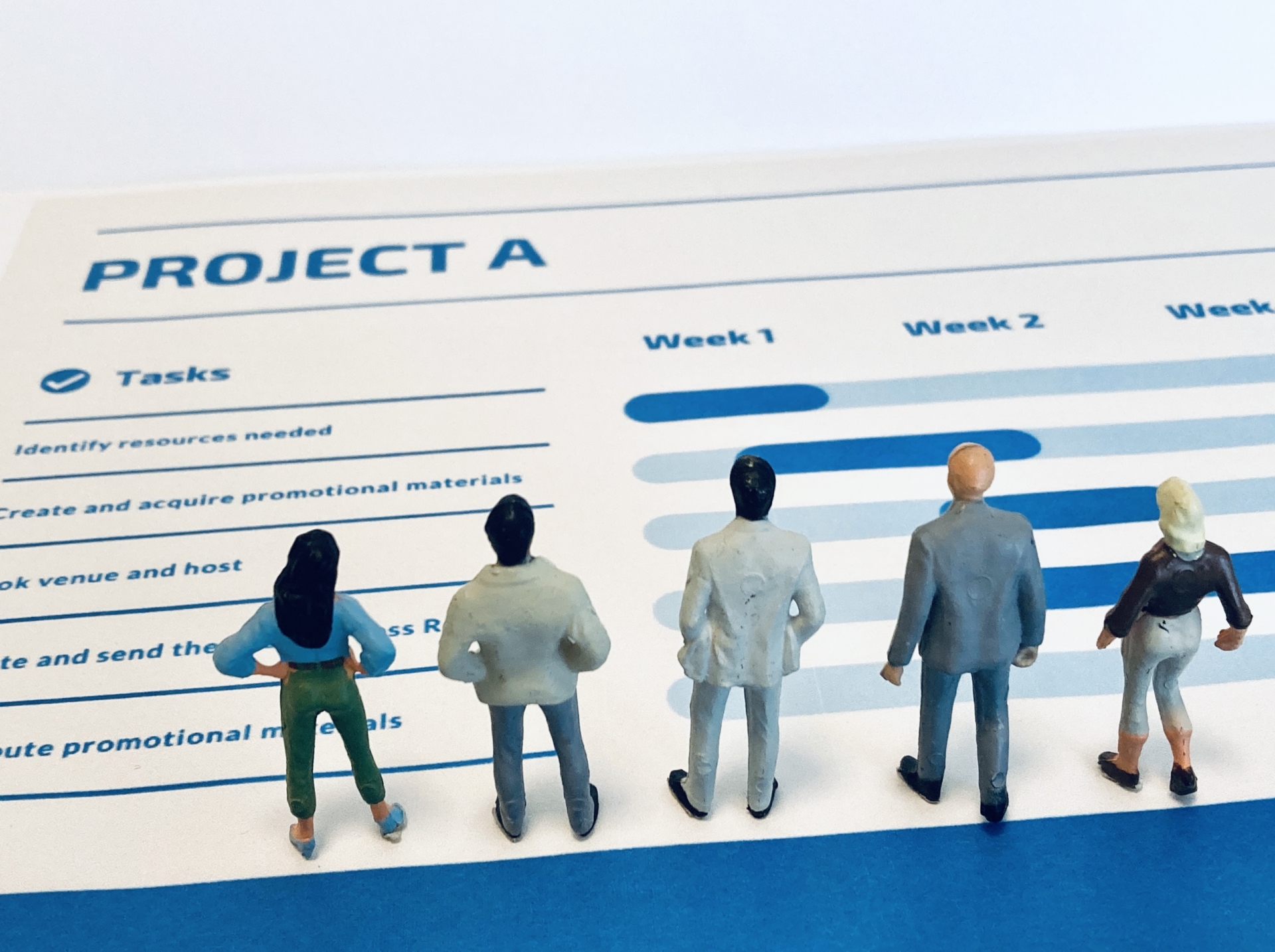RFPم‚’ه®ںéڑ›مپ«è¨ک載مپ™م‚‹éڑ›مپ«وٹ‘مپˆم‚‹مƒم‚¤مƒ³مƒˆم‚„و³¨و„ڈ点
ن»¥ه‰چمپ®è¨کن؛‹مپ§RFPمپ®و„ڈه‘³مپ¨RFPن½œوˆگمپ®ه؟…è¦پو€§ï¼ˆمƒ،مƒھمƒƒمƒˆï¼‰م‚’è¨ک載مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
مپ“مپ®è¨کن؛‹مپ§مپ¯م€پRFPم‚’ه®ںéڑ›مپ«è¨ک載مپ™م‚‹éڑ›مپ«وٹ‘مپˆم‚‹مƒم‚¤مƒ³مƒˆم‚„و³¨و„ڈ点م‚’è¨ک載مپ—مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ™
- RFPم‚’è¨ک載مپ™م‚‹éڑ›مپ«وٹ‘مپˆم‚‹مپ¹مپچمƒم‚¤مƒ³مƒˆ
- م‚·م‚¹مƒ†مƒ هŒ–م‚’è،Œمپ†مپ«è‡³مپ£مپں背و™¯
- ن¾é ¼مپ™م‚‹م‚¹م‚³مƒ¼مƒ—(範ه›²ï¼‰
- 連وگ؛مپ™م‚‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپھمپ©مپŒمپ‚م‚Œمپ°م€پمپم‚Œم‚‰مپ®وƒ…ه ±م‚‚مپ¾مپ¨م‚پمپ¦وڈگç¤؛
- é‡چè¦پ視مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م€په¦¥هچ”مپ§مپچم‚‹ن؛‹
- مپ¾مپ¨م‚پ
RFPم‚’è¨ک載مپ™م‚‹éڑ›مپ«وٹ‘مپˆم‚‹مپ¹مپچمƒم‚¤مƒ³مƒˆ
ن»¥ه‰چمپ®è¨کن؛‹ï¼ˆRFPمپ¨مپ¯ï¼ںم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛م‚’é–‹ç™؛ن¼ڑ社مپ«ن¾é ¼مپ™م‚‹éڑ›مپ«و؛–ه‚™مپ™مپ¹مپچمپ“مپ¨ï¼‰مپ§مپ¯è¦پ点مپ¨مپ—مپ¦ن»¥ن¸‹مپ®م‚ˆمپ†مپ«è¨ک載مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
مƒ»م‚·م‚¹مƒ†مƒ هŒ–م‚’è،Œمپ†مپ«è‡³مپ£مپں背و™¯ï¼ˆمپھمپœم‚·م‚¹مƒ†مƒ هŒ–م‚’è،Œمپ†مپ®مپ‹ï¼ں)
مƒ»ن¾é ¼مپ™م‚‹م‚¹م‚³مƒ¼مƒ—(範ه›²ï¼‰ (م‚·م‚¹مƒ†مƒ هŒ–م‚’è،Œمپ†ç¯„ه›²م€‚مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆم‚’進م‚پم‚‹مپ«مپ‚مپںمپ£مپ¦مپ®ن¾é ¼مپ—مپںمپ„ه½¹ه‰²ï¼‰
مƒ»é€£وگ؛مپ™م‚‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپھمپ©مپŒمپ‚م‚Œمپ°م€پمپم‚Œم‚‰مپ®وƒ…ه ±م‚‚مپ¾مپ¨م‚پمپ¦وڈگç¤؛(ن»–مپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¨مپ®é€£وگ؛مپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپھمپ„مپ¨مپ§مپ¯è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹم‚‚難وک“ه؛¦م‚‚éپ•مپ„مپ¾مپ™ï¼‰
مƒ»é‡چè¦پ視مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م€په¦¥هچ”مپ§مپچم‚‹ن؛‹
مپ“مپ“مپ§مپ¯مپم‚Œمپم‚Œمپ«مپ¤مپ„مپ¦م‚ˆم‚ٹ詳مپ—مپڈه؟…è¦پو€§م‚„مƒم‚¤مƒ³مƒˆم‚’è¨ک載مپ—مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ™م€‚
م‚·م‚¹مƒ†مƒ هŒ–م‚’è،Œمپ†مپ«è‡³مپ£مپں背و™¯ï¼ˆمپھمپœم‚·م‚¹مƒ†مƒ هŒ–م‚’è،Œمپ†مپ®مپ‹ï¼ں)
م‚ˆمپڈ見م‚‹RFP(مپ¨مپ„مپ†م‚ˆم‚ٹمپ¯é–‹ç™؛مپ®è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹن¾é ¼ï¼‰مپ§مپ¯م€پو¬²مپ—مپ„و©ں能مپ«مپ¤مپ„مپ¦و›¸مپ‹م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ن؛‹مپŒه¤ڑمپ„مپ§مپ™م€‚
و©ں能م‚’ç¤؛مپ—مپ¦م‚‚م‚‰مپˆم‚‹مپ®مپ¯م€پ見ç©چم‚‚م‚ٹم‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹é–‹ç™؛ن¼ڑ社مپ‹م‚‰مپ—مپںم‚‰éه¸¸مپ«مپ‚م‚ٹمپŒمپںمپ„مپ®مپ§مپ™مپŒم€پو©ں能مپ¨مپ¯èھ²é،Œم‚’解و±؛مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®م€Œو‰‹و®µم€چمپ§مپ‚م‚ٹم€Œç›®çڑ„م€چمپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚
ç›®çڑ„م‚’و£مپ—مپڈçگ†è§£مپ—مپھمپ„çٹ¶و³پمپ§و‰‹و®µمپ§مپ‚م‚‹و©ں能م‚’é–‹ç™؛مپ—مپ¦م‚‚م€پو©ں能مپ¯ه®ںçڈ¾مپ—مپںمپŒçµگه±€èھ²é،Œمپ¯è§£و±؛مپ—مپھمپ„مپھم‚“مپ¦مپ“مپ¨م‚‚مپ‚م‚ٹم€پمپمپ®ه ´هگˆمƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ¯و„ڈه‘³مپŒمپھمپ‹مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ«مپھم‚ٹم€په¤±و•—مپ—مپ¦مپ—مپ¾مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپمپ†مپھم‚‰مپھمپ„مپںم‚پمپ«م€پRFPم‚’ن½œوˆگمپ™م‚‹ه ´هگˆمپ«مپ¯م€پمپ¾مپڑم€Œمپھمپœم‚·م‚¹مƒ†مƒ هŒ–م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹مپ«è‡³مپ£مپںمپ®مپ‹م€چم‚’èھ¬وکژمپ—مپ¦é ‚مپڈمپ“مپ¨م‚’مپٹه‹§م‚پمپ—مپ¾مپ™م€‚
مپمپ®مپ†مپˆمپ§م€پRFPن½œوˆگهپ´مپ¨مپ—مپ¦è€ƒمپˆمپںو©ں能ن¸€è¦§ï¼ˆèھ²é،Œمپ®è§£و±؛ç–)مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ§مپ‚م‚Œمپ°م€پمپم‚Œم‚‚هگˆم‚ڈمپ›مپ¦è¨ک載مپ—مپ¦é ‚مپڈمپ¨م€پ見ç©چم‚‚م‚ٹم‚„وڈگو،ˆم‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹é–‹ç™؛ن¼ڑ社مپ¯çگ†è§£مپ—م‚„مپ™مپڈم€پ見ç©چم‚‚م‚ٹمپ®و¯”較م‚‚مپ—م‚„مپ™مپڈمپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپںم€پ稀مپ«مپ‚م‚‹مپ®مپŒم€Œèھ²é،Œمپ®é–‹ç™؛و–¹و³•مپ¯م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ§مپ¯مپھمپڈم€پSaaSم‚„مƒ‘مƒƒم‚±مƒ¼م‚¸è£½ه“پمپ®ه°ژه…¥م€چمپ§مپ‚م‚‹مپ¨مپ„مپ†م‚±مƒ¼م‚¹مپ§مپ™م€‚
مپ“م‚Œمپ¯م€پم€Œم‚·م‚¹مƒ†مƒ هŒ–م‚’è،Œمپ†مپ«è‡³مپ£مپں背و™¯م€چمپŒمپچمپ،م‚“م‚’و›¸مپ‹م‚Œم‚Œمپ°è‰¯مپ„مپ®مپ§مپ™مپŒم€پم€ŒSaaSم‚„مƒ‘مƒƒم‚±مƒ¼م‚¸è£½ه“پمپ®ه°ژه…¥مپ§مپ¯مپھمپڈم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛م‚’éپ¸وٹمپ™م‚‹م€چمپ®مپ§مپ‚م‚Œمپ°م€پمپم‚Œم‚‚هگˆم‚ڈمپ›مپ¦èھ¬وکژمپ—مپ¦é ‚مپ‘م‚‹مپ¨è‰¯مپ„مپ‹مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™م€‚
ن¾‹م‚’وŒ™مپ’م‚‹مپ¨ن»¥ن¸‹مپ®م‚ˆمپ†مپھو„ںمپکمپ§مپ™م€‚
م€Œ2ه¹´ه‰چمپ«م€‡م€‡مپ¨مپ„مپ†èھ²é،Œم‚’解و±؛مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«â–³â–³مپ¨مپ„مپ†مƒ‘مƒƒم‚±مƒ¼م‚¸م‚’هˆ©ç”¨مپ—مپںمپŒم€پأ—أ—مپ®ه•ڈé،ŒمپŒç™؛ç”ںمپ—م€پمپ“مپ®مƒ‘مƒƒم‚±مƒ¼م‚¸مپ§مپ¯â– â– مپ®مپںم‚پ解و±؛مپŒه›°é›£مپ¨مپ„مپ†هˆ¤و–مپ«è‡³مپ£مپںم€‚مپمپ®مپںم‚پم€پن»ٹه›مپ¯و–°مپںمپ«è‡ھه‰چمپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’é–‹ç™؛مپ™م‚‹ن؛‹مپ¨مپ—مپںم€‚م€چ
ن¾é ¼مپ™م‚‹م‚¹م‚³مƒ¼مƒ—(範ه›²ï¼‰ (م‚·م‚¹مƒ†مƒ هŒ–م‚’è،Œمپ†ç¯„ه›²م€‚مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆم‚’進م‚پم‚‹مپ«مپ‚مپںمپ£مپ¦مپ®ن¾é ¼مپ—مپںمپ„ه½¹ه‰²ï¼‰
مپ“مپ†و›¸مپڈمپ¨م€Œم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛م‚’ن¾é ¼مپ—مپںمپ„م‚“مپ م€چمپ¨مپ“م‚Œم‚’èھمپ¾م‚Œمپ¦مپ„م‚‹و–¹مپ¯و€مپ†مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ—مپ‹مپ—م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ«مپ¯مپ„مپڈمپ¤م‚‚مپ®مƒ—مƒم‚»م‚¹مپŒمپ‚م‚ٹم€پçڈ¾çٹ¶مپŒمپ©مپ†مپھمپ®مپ‹م€پمپ¾مپںمپ©مپ®ه·¥ç¨‹م‚’ن¾é ¼مپ—مپںمپ„مپ®مپ‹مپ«م‚ˆم‚ٹ費用مپ¯ه¤§مپچمپڈه¤‰م‚ڈم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
ه¤ڑمپڈمپ®ه ´هگˆم€پمپ“مپ†مپ„مپ£مپںوƒ…ه ±مپŒوکژç¤؛مپ•م‚Œمپھمپ„م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ®ه ´هگˆم€پé–‹ç™؛ن¼ڑ社مپ‹م‚‰مپ®è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹمپ¯é«کمپڈمپھم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒé«کمپ„مپ§مپ™م€‚
è¨ک載مپ™م‚‹ه ´هگˆمپ‹ن»¥ن¸‹مپ®م‚ˆمپ†مپھوƒ…ه ±م‚’è¨ک載مپ™م‚‹مپ®مپŒè‰¯مپ„مپ§مپ™م€‚
مƒ»مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ®è²¬ن»»è€…
مپ“م‚Œم‚’ن¾é ¼è€…هپ´مپŒç«‹مپ¦م‚‰م‚Œم‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹م€‚
م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®è²¬ن»»è€…مپ¯م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛ن¼ڑ社مپ‹م‚‰مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمƒمƒچمƒ¼م‚¸مƒ£مƒ¼مپŒéپ¸ه‡؛مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™مپŒم€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ ن¼ڑ社مپ‹م‚‰مپ®وڈگو،ˆم‚„ç¢؛èھچمپ«ه¯¾مپ—مپ¦و‰؟èھچم‚„مƒ•م‚£مƒ¼مƒ‰مƒگمƒƒم‚¯مپ—مپںم‚ٹمپ™م‚‹مپ®مپ¯é€ڑه¸¸ن¾é ¼è€…هپ´مپ§مپ™م€‚
آ مپمپ®çµگوœè²¬ن»»م‚’وŒپمپ¤مپ®مپŒمƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆè²¬ن»»è€…مپ§مپ‚م‚ٹم€پمپ“م‚Œم‚’م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛ن¼ڑ社مپ«è² م‚ڈمپ›م‚‹مپ®مپ¯é€ڑه¸¸مپ‚م‚ٹه¾—مپ¾مپ›م‚“مپŒم€پمƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆè²¬ن»»è€…م‚’ç«‹مپ¦م‚‰م‚Œمپھمپ„م‚ˆمپ†مپھن¾é ¼è€…مپ®ه ´هگˆم€پè³ھه•ڈمپ—مپ¦م‚‚ه›ç”مپŒè؟”مپ£مپ¦مپ“مپھمپ‹مپ£مپںم‚ٹو›–وک§مپ مپ£مپںم‚ٹمپ§م€پمƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپŒمپھمپ‹مپھمپ‹é€²مپ¾مپھمپ„مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپŒن؛ˆوƒ³مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚
آ آ مپ“مپ†مپ„مپ£مپںمپ“مپ¨مپŒه‡؛و¥م‚‹è¦په“،م‚’ن¾é ¼è€…هپ´مپ§و؛–ه‚™مپ§مپچم‚‹مپ‹مپ§مپچمپھمپ„مپ‹مپ§م€پé–‹ç™؛ن¼ڑ社مپ‹م‚‰ه‡؛مپ¦مپڈم‚‹è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹمپ®é‡‘é،چمپŒه¤‰م‚ڈمپ£مپ¦مپچمپںم‚ٹم€پم‚‚مپ—مپڈمپ¯وڈگو،ˆمپ—مپ¦م‚‚م‚‰مپˆم‚‹و•°مپ«ه½±éں؟مپŒه‡؛م‚‹مپ‹م‚‚مپ—م‚Œمپ¾مپ›م‚“م€‚
آ آ
مƒ»é–¢م‚ڈمپ£مپ¦و¬²مپ—مپ„ه·¥ç¨‹م‚„ه½¹ه‰²
مپ©مپ“مپ‹م‚‰مپ©مپ“مپ¾مپ§م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«é–¢م‚ڈمپ£مپ¦و¬²مپ—مپ„مپ‹مپ§مپ™م€‚
ç°،هچکمپ«و›¸مپڈمپھم‚‰م€Œè¦پن»¶ه®ڑ義م€چم€Œè¨è¨ˆم€چم€Œé–‹ç™؛مپٹم‚ˆمپ³مƒ†م‚¹مƒˆم€چم€Œمƒھمƒھمƒ¼م‚¹م€چم‚„م€Œهڈ—ه…¥مƒ†م‚¹مƒˆو”¯وڈ´م€چمپھمپ©م€‚
آ مƒھمƒھمƒ¼م‚¹مپ—مپ¦مپ‹م‚‰مپ®ن؛‹م‚’考مپˆم‚‹مپھم‚‰م€Œن؟ه®ˆم€چم€Œéپ‹ç”¨م€چمپھمپ©م‚‚ه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚
آ آ
ن¸ٹè¨کمپ«وکژç¤؛çڑ„مپ«ه…¥م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ„م‚‚مپ®مپ¨مپ—مپ¦مپ¯م€پم€Œم‚¤مƒ³مƒ•مƒ©è¨è¨ˆمƒ»و§‹ç¯‰م€چم‚„م€Œهˆوœںمƒ‡مƒ¼م‚؟ن½œوˆگم€چم€Œمƒ‡مƒ¼م‚؟移è،Œم€چمپھمپ©م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
آ آ مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ«م‚ˆمپ£مپ¦مپ¯ه؟…è¦پمپ®مپھمپ„م‚‚مپ®م‚‚مپ‚م‚‹مپ‹م‚‚مپ—م‚Œمپ¾مپ›م‚“مپŒم€پن½•م‚‚è¨ک載مپŒمپھمپ„ه ´هگˆمپ¯ه…¨مپ¦ه؟…è¦پمپ¨مپ„مپ†ه‰چوڈگمپ§é–‹ç™؛ن¼ڑ社هپ´مپ¯è¦‹ç©چم‚‚م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
آ آ ن»®مپ«ه…¨éƒ¨ن¾é ¼مپ—مپںمپ„مپ¨مپ—مپ¦م‚‚م€پمپ“مپ†مپ„مپ£مپںوƒ…ه ±م‚’è¨ک載مپ—مپ¦مپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پé–‹ç™؛ن¼ڑ社مپ‹م‚‰مپ™م‚‹مپ¨م€Œمپ“مپ®ن¾é ¼è€…مپ¯مپ‚م‚‹ç¨‹ه؛¦مپ¯هˆ†مپ‹مپ£مپ¦مپ„م‚‹م‚“مپ مپھم€چمپ¨و€مپ„م€پن½•م‚‚è¨ک載مپŒمپھمپ„م‚ˆم‚ٹمپ¯è؛«و§‹مپˆمپھمپڈمپھم‚‹مپ‹مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™م€‚(مپٹ見ç©چم‚ٹمپ®é‡‘é،چمپŒوٹ‘مپˆم‚‰م‚Œم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒن¸ٹمپŒمپ£مپںم‚ٹم€پوڈگو،ˆو•°مپŒه¢—مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒè‹¥ه¹²مپ§مپ™مپŒوœںه¾…مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚)
連وگ؛مپ™م‚‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپھمپ©مپŒمپ‚م‚Œمپ°م€پمپم‚Œم‚‰مپ®وƒ…ه ±م‚‚مپ¾مپ¨م‚پمپ¦وڈگç¤؛(ن»–مپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¨مپ®é€£وگ؛مپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپھمپ„مپ¨مپ§مپ¯è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹم‚‚難وک“ه؛¦م‚‚éپ•مپ„مپ¾مپ™ï¼‰
مپ“م‚Œمپ¯è¦‹ه‡؛مپ—مپ®é€ڑم‚ٹمپ§مپ™مپŒم€پ特مپ«é€£وگ؛مپ™م‚‹ه¯¾è±،مپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپŒم€پ独è‡ھé–‹ç™؛مپ—مپ¦مپ„م‚‹م‚ˆمپ†مپھهں؛ه¹¹م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپھمپ©مپ§مپ‚مپ£مپںم‚ٹمپ™م‚‹مپ¨م€په·¥و•°مپŒه¤§مپچمپڈه¢—مپˆم‚‹è¦په› مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپ“مپ†مپ„مپ£مپںوƒ…ه ±م‚’وڈگو،ˆو®µéڑژمپ§è¨ک載مپ—مپھمپ„مپ¨è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹمپŒوٹ‘مپˆم‚‰م‚Œمپںم‚ٹوڈگو،ˆمپŒه¢—مپˆمپںم‚ٹمپ™م‚‹مپ‹م‚‚مپ—م‚Œمپ¾مپ›م‚“مپŒم€پمپ„مپ–مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپŒé–‹ه§‹مپ—مپںم‚‰è©±مپŒéپ•مپ£مپںمپ¨é–‹ç™؛ن¼ڑ社مپ¨وڈ‰م‚پم€پمƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپŒمپ¨م‚“وŒ«مپ™م‚‹مƒھم‚¹م‚¯م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپ§مپ™مپ®مپ§م€پé‡چè¦پمپھوƒ…ه ±مپ§مپ™مپ®مپ§و±؛مپ¾مپ£مپ¦مپ„مپںم‚‰RFPمپ«è¨ک載مپ—مپ¦مپٹمپ„مپںو–¹مپŒè‰¯مپ„مپ§مپ™م€‚
é‡چè¦پ視مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م€په¦¥هچ”مپ§مپچم‚‹ن؛‹
مپ“م‚Œم‚‚è¨ک載مپ®é€ڑم‚ٹمپ§مپ™مپŒم€پن»¥ن¸‹مپ«é …ç›®مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ©م‚ŒمپŒه„ھه…ˆن؛‹é …مپ§مپ©م‚ŒمپŒه„ھه…ˆمپ§مپھمپ„مپ‹م‚’وکژç¢؛مپ«مپ™م‚‹مپ¨م€پوڈگو،ˆمپŒهڈ—مپ‘م‚„مپ™مپڈمپھمپ£مپںم‚ٹم€پمƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆé€²è،Œن¸مپ®مƒڈمƒ³مƒ‰مƒھمƒ³م‚°م‚‚مپ—م‚„مپ™مپڈمپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مƒ»ه“پè³ھ
مƒ»ن؛ˆç®—
مƒ»م‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«
ن¸ٹè¨کم‚’QCD(Q=Qualityم€پC=Costم€پD=Deliverly)مپ¨م‚‚مپ„مپ„مپ¾مپ§مپ™مپŒم€په…¨مپ¦مپŒé«کمپ„هں؛و؛–مپ§مپ¾مپ¨مپ¾مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ¯م€پé€ڑه¸¸مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚(ه“پè³ھمپŒé«کمپڈم€پ見ç©چم‚‚م‚ٹمپŒه®‰مپڈم€پç´چوœںمپŒçںمپ„م€پمپ¨مپ„مپ†و„ڈه‘³ï¼‰
مپ‚م‚‹مپ¨مپ—مپںم‚‰م€پè¦پن»¶مپ«هگˆè‡´مپ—مپںمƒ‘مƒƒم‚±مƒ¼م‚¸مپŒمپ‚مپ£مپںم‚ٹم€پéپژهژ»é–‹ç™؛مپ—مپںم‚‚مپ®م‚’ن½؟مپ„مپ¾م‚ڈمپ›م‚‹مپھمپ©مپ¨مپ„مپ£مپںه ´هگˆمپ مپ‘مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
م‚‚مپ،م‚چم‚“مپمپ†مپ„مپ†مپ“مپ¨م‚‚مپ‚م‚‹مپ¨مپ¯و€مپ†مپ®مپ§م€په…¨مپ¦م‚’ه„ھه…ˆمپ™م‚‹مپ¨مپ„مپ†هˆ¤و–م‚‚وڈگو،ˆو™‚مپ«مپ¯è‰¯مپ„مپ‹م‚‚مپ—م‚Œمپ¾مپ›م‚“مپŒم€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ¯ن¸چç¢؛ه®ںو€§م‚„مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«مپ¨مپ®وˆ¦مپ„مپ§م‚‚مپ‚م‚‹مپ®مپ§م€پمپمپ†مپ„مپ£مپںéڑ›مپ«مپ©مپ†مپ„مپ£مپںهˆ¤و–م‚’مپ™م‚‹مپ‹مپ¨مپ„مپ†و„ڈه‘³مپ§م€په„ھه…ˆمپ™مپ¹مپچمپ“مپ¨م‚„ه„ھه…ˆمپ—مپھمپ„ن؛‹م‚’وکژç¢؛مپ«مپ—مپ¦مپٹمپڈمƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¯مپ‚م‚‹مپ¨è¨€مپˆمپ¾مپ™م€‚
ه…¨مپ¦مپ®ن؛؛مپ«مƒ“م‚¸مƒچم‚¹م‚¯مƒ©م‚¹م‚„مƒ•م‚،مƒ¼م‚¹مƒˆم‚¯مƒ©م‚¹مپ¯ه؟…è¦پمپھمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ—م€پè»ٹمپ§م‚‚3مƒٹمƒ³مƒگمƒ¼مپ®مƒ¯مƒ³مƒœمƒƒم‚¯م‚¹مپŒو¬²مپ—مپ„ن؛؛م‚‚مپ„م‚Œمپ°è»½è‡ھه‹•è»ٹمپ§è‰¯مپ„ن؛؛م‚‚مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ„مپڑم‚Œم‚‚ç›®çڑ„هœ°مپ«ç€مپڈمپ¨مپ„مپ†ç›®çڑ„م‚„م€پن؛؛م‚’ن¹—مپ›مپ¦èµ°م‚‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ¯éپ”وˆگمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پ金é،چمپ«مپ¯مپ‹مپھم‚ٹمپ®éپ•مپ„مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ¯èھ¬وکژمپ™م‚‹مپ¾مپ§م‚‚مپھمپ„مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپ¨م‚پ
مپ“مپ®è¨کن؛‹مپ§مپ¯RFPم‚’è¨ک載مپ™م‚‹éڑ›مپ«وٹ‘مپˆمپ¦مپٹمپڈمƒم‚¤مƒ³مƒˆم‚’مپ¾مپ¨م‚پمپ¦èھ¬وکژمپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
ç¹°م‚ٹè؟”مپ—مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™مپŒم€پRFPم‚’ن½œوˆگمپ™م‚‹مپ«مپ¯و™‚é–“م‚„ه¤ڑه°‘مپ®ه°‚é–€çں¥èکم‚‚ه؟…è¦پمپ§مپ™مپŒم€پمپم‚Œم‚’م‚„م‚‹مپ مپ‘مپ®مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مƒھم‚±م‚¹م‚؟مپ§مپ¯RFPن½œوˆگمپ®مپںم‚پمپ®م‚¢مƒ‰مƒگم‚¤م‚¹مپھمپ©م‚‚م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’è،Œمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™مپ®مپ§م€پم‚¢م‚«م‚¦مƒ³مƒˆç™»éŒ²مپ®مپ†مپˆمپ”ç›¸è«‡é ‚مپ‘م‚Œمپ°مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™م€‚
→م‚¢م‚«م‚¦مƒ³مƒˆï¼ˆن¼ڑه“،)登録مپ¯مپ“مپ،م‚‰
â– RFPمپ«é–¢مپ™م‚‹è¨کن؛‹
مƒ»RFPمپ¨مپ¯ï¼ںم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛م‚’é–‹ç™؛ن¼ڑ社مپ«ن¾é ¼مپ™م‚‹éڑ›مپ«و؛–ه‚™مپ™مپ¹مپچمپ“مپ¨
مƒ»RFPمپ£مپ¦ن½•ï¼ںم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®وڈگو،ˆن¾é ¼و›¸مپ«مپ¤مپ„مپ¦ه¾¹ه؛•è§£èھ¬