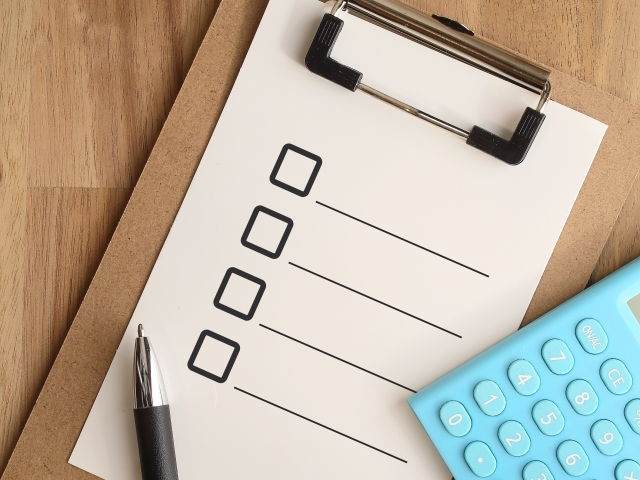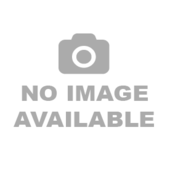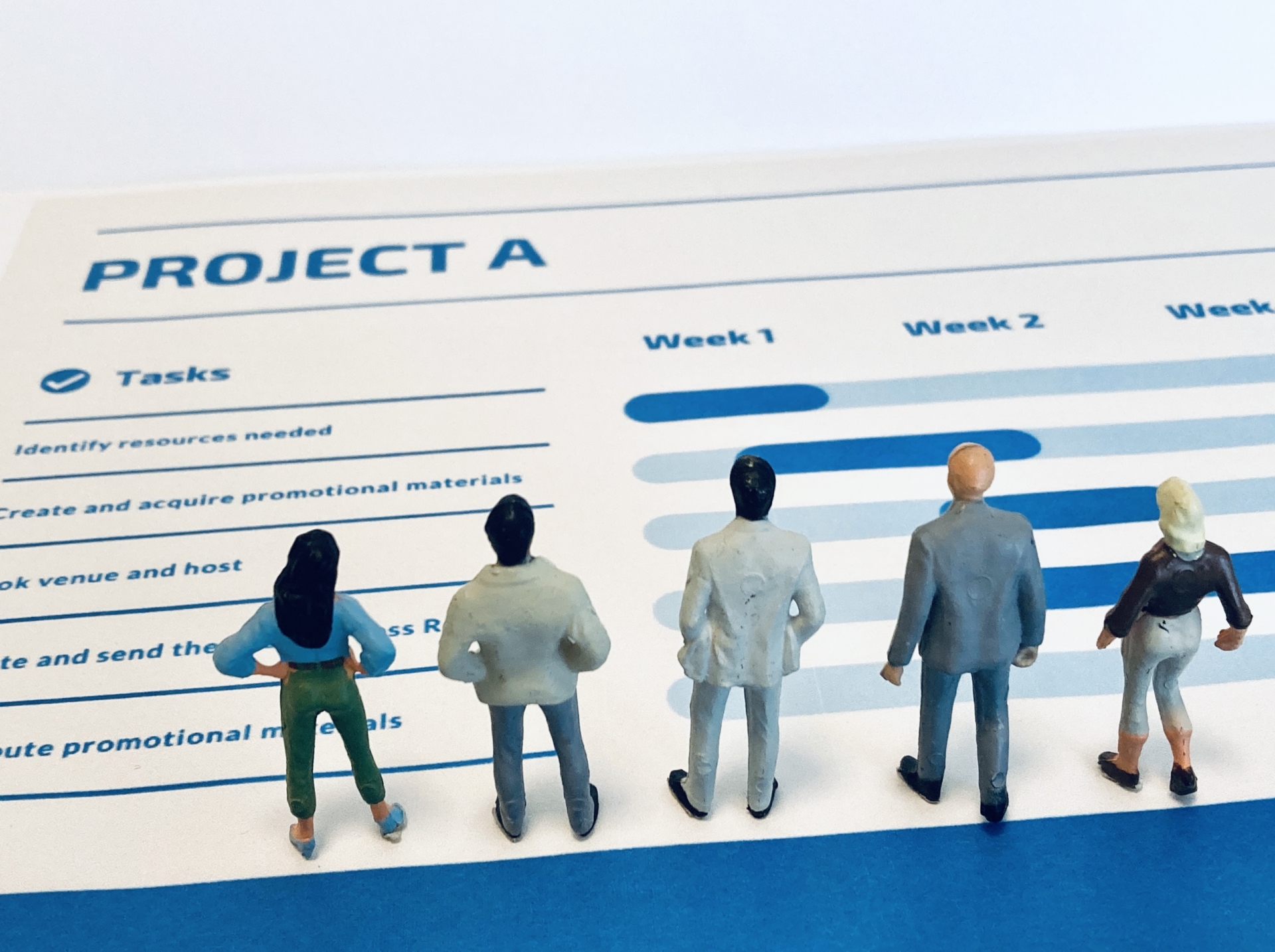プロトタイプとは?その他にも類似したシステム開発や関連用語を徹底解説!
システム開発をする上で、しっかりと出来上がるまでプロセスがありますが、そのプロセスの中で試作品というのはとても大事になってきます。
「失敗は成功のもと」という言葉にあるように、いくつもの失敗・試行錯誤があり様々なものが出来上がります。
ここで取り上げるシステム開発もプロトタイプが重要になっており、プロトタイプを元にした開発や関連用語を徹底解説します!
- プロトタイプとは?
- プロトタイプ開発
- 用語の説明
- プロトタイピングが有用な理由と有効なシーン
- プロトタイピングのメリットデメリット
プロトタイプとは?
プロトタイプ(prototype)とは、「原型」「試作品」という意味です。
ITの分野では、ハードウェア開発の際の量産前の試作品や、動作や機能を検証するために最小限の規模で試作されたソフトウェアなどのことも指します。
プロトタイプを作る目的
あらゆる開発や制作での、早い段階で製品・サービスの改善点や問題点を見つけて、より良い製品・サービスにつなげることです。
また、0から1へと新しいアイデアに対しては、プロトタイプを作成し、実物のイメージを見える形にすることで、再現性が高められます。
プロトタイプを行わずに量産した場合は、開発時に気づかなかった問題が市場に出てから露呈し、顧客の満足度を損なう可能性もあるのです。
このため、開発においてプロトタイピングは重要なプロセスといえます。
また、大量生産が前提となるビジネスや製造業では、いくつかのプロトタイプを制作して品質や完成度を高めながら、実際に市場に流通させる「市販品」へと試行錯誤していくことが一般的になります。
これは、システム開発でも同じことであると考えて間違いないです。
プロトタイプ開発

具体的に説明すると、一般的なソフトウェア開発手法の1つであるプロトタイプ開発は、開発段階で制作予定のシステムの簡易版を設計・開発・テストをすることを繰り返し、そのフィードバックを元に最終的なプロダクト(製品)の完成を目指す開発手法になります。
実際に動作するテストシステムを開発・改善しながら作成するので、最終的な完成イメージが明確になっていない場合にも、おおよそのイメージから初期開発が進められたり、テストシステムからプロダクトの完成イメージがつかみやすかったりする点が特徴です。
プロトタイプ開発の目的と例
目的としては、プロジェクトのリスクと開発にかかるコストの低減につなげることができます。
理想のシステムを開発していくためには、アウトプットしたものを確認・評価して起動修正を少しずつ行っていくので、少しずつ修正をすることが大事になるのです。
例としては、自動車産業や任天堂などが提供しているゲーム機のSwitchなどは、0から1のイメージをまずプロトタイプとして具現化して、そこから試行錯誤を重ねて完成し、消費者に提供されているのです。
用語の説明
プロトタイプの類義語としてMVP(Minimum Viable Product)とPoC(Proof Concep)というものがあります。
MVPは求められている最小限の製品といったようなニュアンスで、プロトタイプと完全に同じ意味ではないですが、かなり近い意味で使われることが多いです。
また、PoCは、考えているもので実現可能かどうか実際にプロトタイプをつくってみたり、作ってみて実際に良いサービスかどうか、コアな機能のみを実装してテストユーザーに評価してもらうという使い方がされます。
具体的な解説は下記で徹底解説します!
MVPとPoC
MVPは、実用最小限の製品という意味で、想定するユーザーに対して「コアとなる価値」を提供でき、有効なフィードバックが得られるだけの最小限の機能を持つ製品のことを指します。
仮説に基づいたコアとなる最小限の機能を低コスト・短期間で実装し、それを用いて実際にユーザーからのフィードバックを得ることにより、低リスクかつ早い段階での検証が可能です。
このアプローチをすることで、検証が正しいかどうかを早期に実証した上で開発に反映することができることから、リスクを抑えつつ成功確度を高めることができるのです。
仮説の検証に必要な最小限のレベルの製品を低コストでいち早く作り上げることがその目的となります。
つまり、大切なのはプロダクト全体の完成度ではなく、「仮説検証に十分な機能が適切に実装されているかどうか」がMVP開発におけるポイントです。
PoCは、概念実証という意味で、新たなデザインやコンセプトの実現可能性やそれによって得られる効果などについて検証することです。
これによって事前に検討したアイデアやコンセプトの実現可能性を見極め、期待した効果が得られると判断できればプロジェクトを進めていくというのが一般的です。
例えば、新規性の高いビジネスを立ち上げる、あるいは革新的な技術を利用するといったとき、本当にそれが実現できるのか、それによって効果が得られるのかを机上の議論のみで判断するのは困難です。
そこで実際に小規模で試作や実装を行い、できあがったものを用いて検証を行うことにより、実現可能性の判断の制度を高めることが可能になるのです。
プロトタイピングが有用な理由と有効なシーン
プロトタイピングは、そもそもリスクを最小化するためです。
逆の方法としては、ウォーターフォールモデルがあります。これを簡単に説明しますと、「要件定義」「基本設計」「詳細設計」「システム実装」「テスト」という流れが開発の基本工程になります。一つひとつの工程を確実に行っていくため後戻りしないのがウォーターフォールモデルになります。この開発法は業務システム開発においてはよく取られる手法です。
一方で、プロトタイピングが用いられるシーンとしては、WEBサービスのように外部の利用者に使ってもらうような不確実性の高い場合、リスクを最小化するためにプロトタイピングが行われる場合が多いです。
また、WEBサービス開発を行う際に、プロトタイピングと違う言葉でアジャイル開発というものがあります。これも説明しますと、システム開発にかかる工程を細かく分けて、短いサイクルで進行していくシステム開発手法の1つです。
ウォーターフォールモデルでは、途中で仕様変更が入ると手戻りが発生し修正に時間がとてもかかるのが問題点に対して、アジャイル開発の場合は、機能レベルを小さな単位で作業を進め、企画からリリースを細かく繰り返すため、ゼロからシステムを開発したり、仕様変更や追加機能が想定されたりする場合などで有効な開発手法になるのです。
プロトタイピングのメリットデメリット

これまでプロトタイピングについて説明してきましたが、ここではプロトタイピングのメリットも上記で少し話しましたが、メリット・デメリットをまとめて徹底解説します!
メリット
プロトタイピングのメリットは全部で4つあります。
1つ目は、手戻りを防ぐこと
早い段階で顧客にプロダクトのイメージを見せることで、顧客のニーズとプロダクトのズレに早期に気づくことができ、完成してからの手戻りを防ぐことができます。
プロトタイピングで気づいたズレを次のプロトタイプに反映させて、徐々にプロダクトを顧客ニーズに近づけていくことができます。
2つ目は、チームメンバー間の認識のズレを防ぐこと
よくソフトウェア開発で作られる要件定義書だけでは、最終形のイメージに不一致が生じる可能性があります。プロトタイプを作ることで、デザイナーやエンジニアが課題を共有したり、互いに合意を取ったりしながら開発を進められます。
このようにメンバーが一体感を持って開発を進められることも一つのメリットといえます。
3つ目は、コスト(時間と費用)削減につながる
開発工程が進むにつれ、方向性を変えることが困難になりえます。プロトタイピングによって、開発の後の工程で変更の発生を減らすことができ、効率的な開発を行うことができます。
これにより、時間と費用の低減につながるのです。
4つ目は、仕様の肥大化を防ぐこと
プロトタイプのユーザーテストでは、評価の優劣が分かれたり、評価されない機能が出たりすることもあります。
最初に仮説の優先順位をつけ、何がソリューション(解決や解答)の核となるかを決めておくと、評価の判断がしやすく、仕様の最適化が図れます。
ユーザーエクスペリエンス(UX:ユーザーが商品やサービスを通して得られる全ての体験)の向上につながります。
デメリット
プロトタイピングのデメリットは、3つあります。
1つ目は、プロジェクトが進まないリスクがあること
プロトタイピングでは、クライアント側がシステムを操作しながら仕様やデザインを決められるため、より希望に沿った完成品を得られるメリットがあります。
ただその一方で、プロトタイプを見せるたびに当初にはなかった要望が出てきて、延々と修正を繰り返す必要があるなど、開発のプロセスが泥沼化するリスクがあります。
2つ目は、開発会社側の負担が大きいこと
プロトタイピングを行う過程では、試作品を何度も制作する必要があり、できるだけ完成度の高い試作品が求められるため、制作者の作業量は多くなります。
さらに、フィードバックを反映することも考えると、その分コストも労力・時間もかかるのです。
3つ目は、大規模なシステム開発には向いていないこと
大規模なシステム開発の場合、関わる関係者は多くなります。
そのため、試作品の検証のために関係者全員がスケジュールを合わせるだけでも大変になります。調整のために工程が後ろにズレてしまうリスクがあるからです。
また、多くの関係者がいると多数の意見が生じて、修正箇所が多くなり、工数が増えたり、スケジュールが遅延したりと、逆に効率が悪くなる可能性があります。
プロトタイピングのメリットを活かすには、プロジェクト自体の適正を見極めることも重要です。